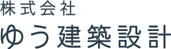設計コンセプトConcept
障害者
障害者の建築計画は大きく変わった 砂山 憲一
1)障害者施設の建築設計
「障害特性への細やかな対応、さらに個別対応へ」「標準化」「コスト」
ゆう建築設計ではこの5年間で20件を超える障害者の建築を計画しました。
そこでの建築計画の特徴は「障害特性への細やかな対応、さらに個別対応」「標準化」「コスト」の3点です。今後の障害者施設の建築計画を行う上で重要なキーワードです。これに支援員の働きやすさ、支援のしやすさが加わります。
1:特性分類の多様化、利用者への理解が個人単位で
障害者の特性分類が施設によって異なります。重度、軽度、強行などの分類から、各利用者の特性をより伝わりやすいい言葉で表すようになっています。特性に対応する建築的工夫も施設ごとの考え方や分類方法に合わせて細かく対応しています。
入居者全員の個人アセスメントを作成する施設も増えてきました。個人への対応を支援で行うのは当然ですが、建築も個人ごとに対応を変えて設計するケースが出てきています。
2:標準化の対象が広がっている「落ち着ける」の標準化まで考える
利用者個人への建築対応が進んでいますが、新たに施設を作る場合入居予定者個人ごとの資料がない場合がほとんどです。利用者の特性の詳細がわからなくても、建築対応は行わなければいけません。
千葉県成田市に竣工した「ゆめふる成田」は自閉症の方のすまいですが、各個室はそれぞれ個別に計画しています。今後入居予定者がわからない場合でも、自閉症の方の個室をいくつかに標準化し、数種類の個室パターンを作っておくことになるでしょう。
成田では「落ち着いて暮す」ことができる建築からの対応を考えました。この例で分かるように、障害特性への建築対応の標準化は、「破壊」「失便」などの項目から、「落ち着かない」「感情が不安定」などへも建築ができる事、行わなければいけないことがあるのではないかと考えるようになってきています。
3:工事費が上昇する中で、特性対応のコストが大きな要素となる
工事費の上昇によって、施設計画を延期せざるを得ない事業者が出てきています。これまで福祉施設の計画では、基本計画段階でコストを検討することは少なかったのですが、この数年コストによって計画内容を変える場合も出てきています。
障害者建築の障害特性への建築対応のコストについて、ゆう設計では細かく算出しています。今後はこのコストを参考にしつつ、建築計画を行うことになります。特性への建築対応の選択にはコストを考慮にいれて決めていくことになります。面積もコストに大きくかかわりますから、建築計画の初期段階から特性対応のプランをどのように作るか考えなければいけません。
2)ゆう建築設計の障害者建築への向き合い方 「建築は支援の一つ」
ゆう建築設計は医療福祉分野の設計を多く行っていますが、障害者施設に対しては他の分野とは違う思いがあります。それは障害者にどのように向き合おうか考えるところから始まったからです。
最初は障害者施設の便所の改修だったのですが、障害者の住まい方を終日見ていくうちに、社会生活のマナーはどうすればよいのだろうと考えました。ドアや壁を壊すことには壊れにくいものを作ればよいが、床に寝転ぶことへは、寝転ばないことを前提とするのか、寝転ぶことを前提として気持ちの良い床材を選ぶのか、どうすればよいのだろう。フィンランドの施設を社員が見に行って、施設には営繕部があり、壊れたところは補修しているところがあることを知り、壊すことで落ち着くなら、壊れる壁でも良いのだろうかと悩みました。
またある施設の方から、建築内容はどのようなものになろうとも、支援できちんと対応できるから、あまり気にしなくても大丈夫だと言われ、建築の役割はあるのだろうかとも考えました。10 年ぐらい前の話です。
この辺りから、なにか欠けていると感じだしていました。それは特性への建築的工夫の整理は多くやっていますが、住み手の思いはどうくみ取ればよいか、その思いにこたえる障害者のすまいはどうすればよいか、を日々の計画で考えるようになりました。20 年以上前に特養の設計を行った時、高齢で意思表示ができない方の個室をどうすればよいかわからないという私の問いにその施設長は「その人の目を見なさい。じっと見ていればわかってきますよ。」と言ってくれました。住み手を見ることから始まるという私たちの思いはここからきています。
今は素直に障害者の住み方に向き合い、施設の方達と議論しながら、住む人達、支援する人が落ち着く、その方たちに合った建築を作っていけばよいと感じています。

※『時空読本No.38』2024年5月発刊 記事